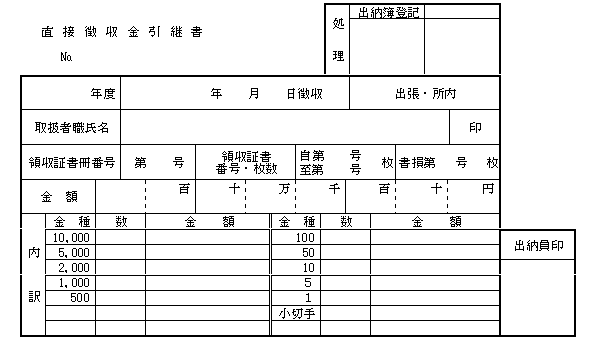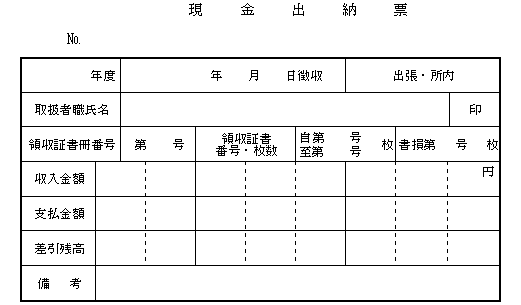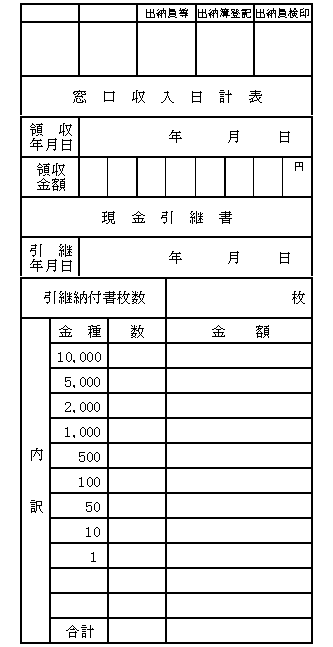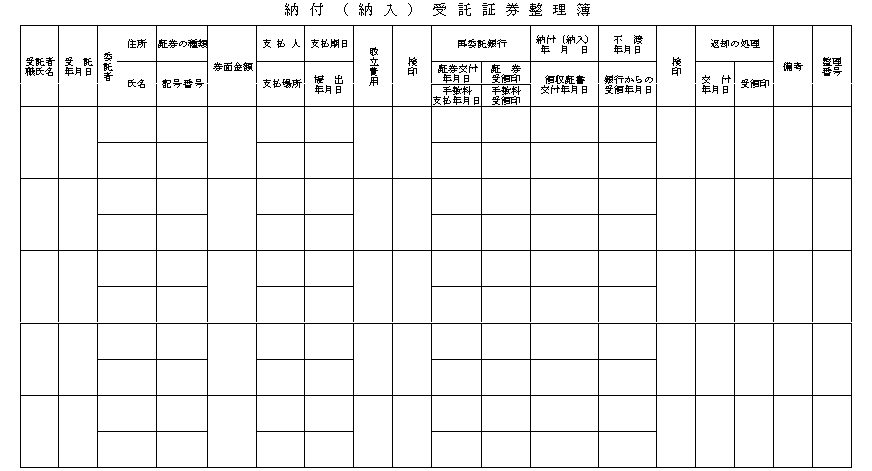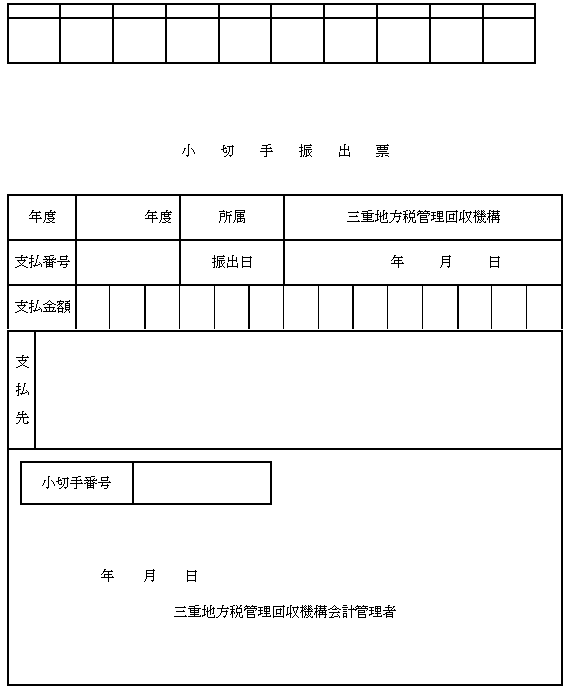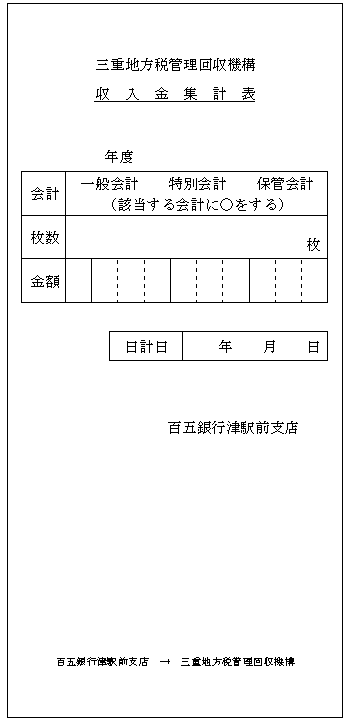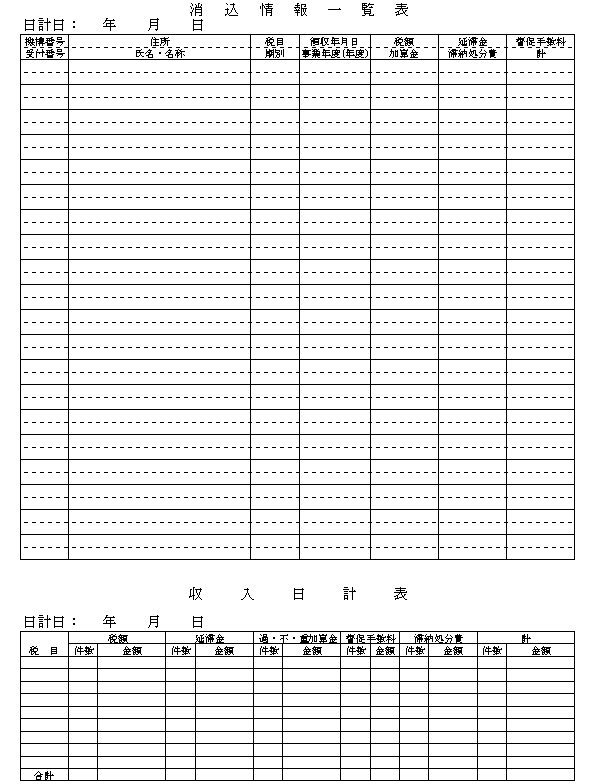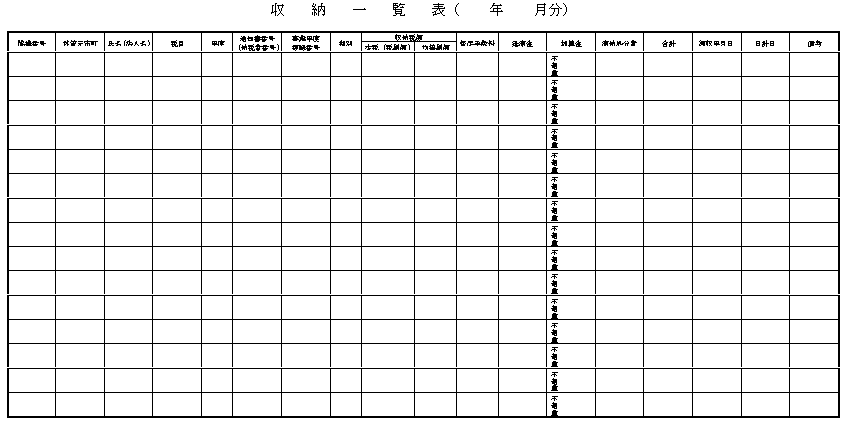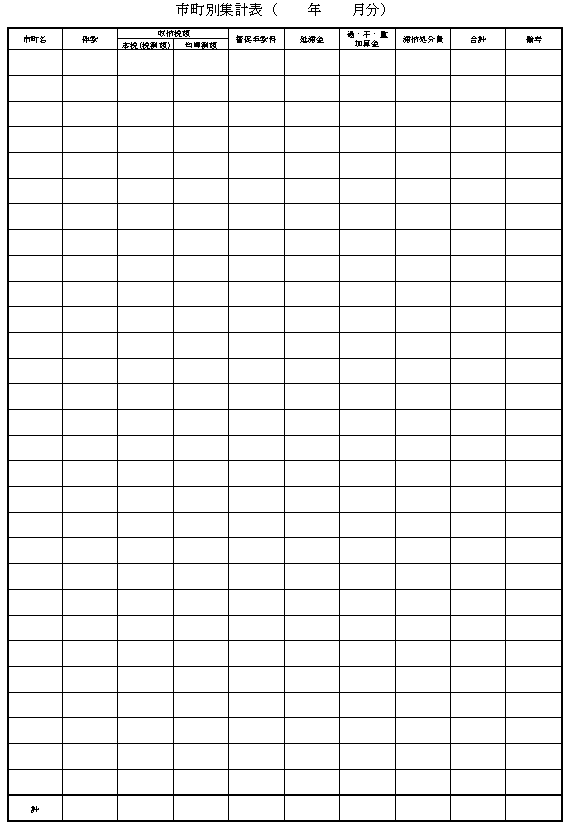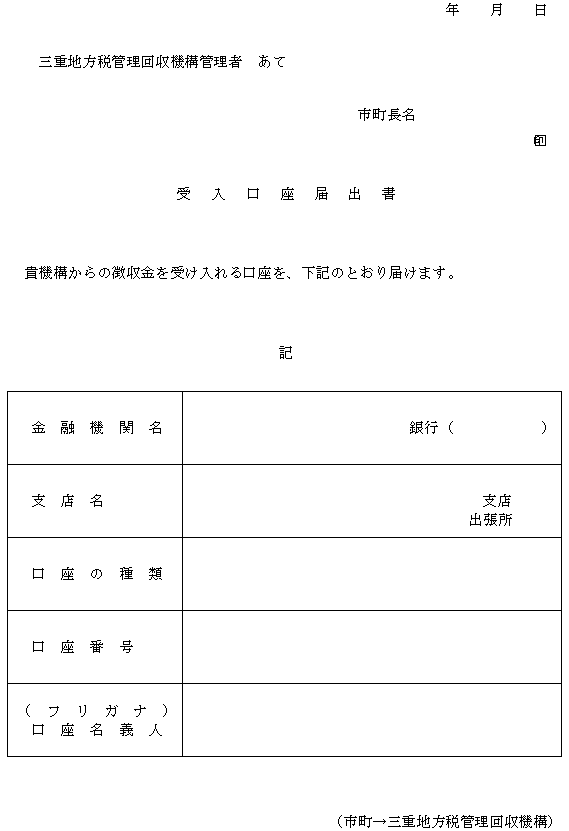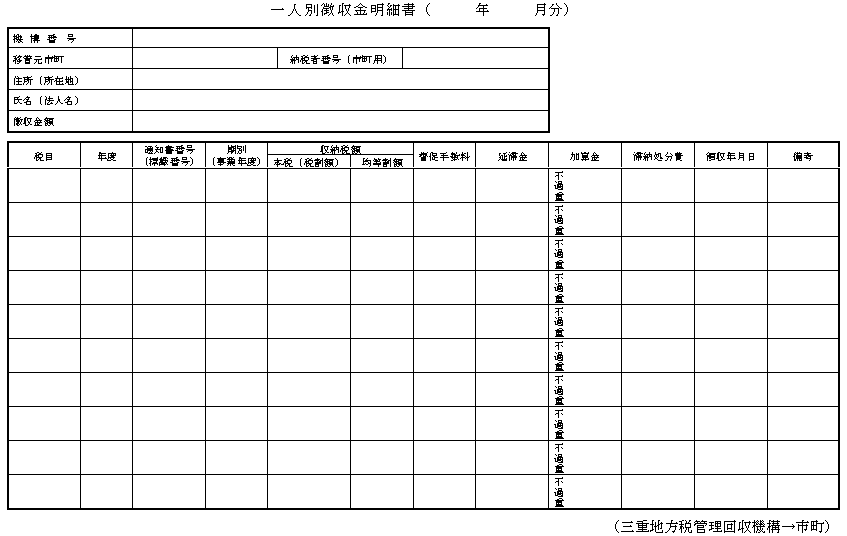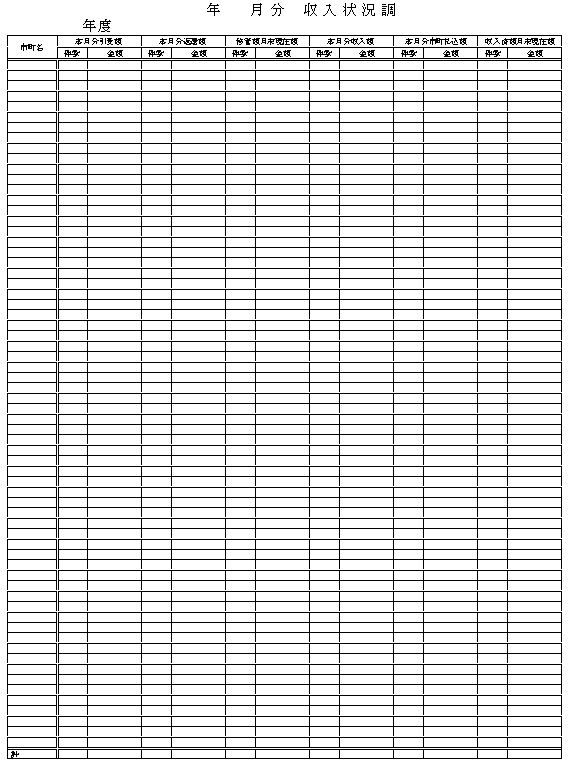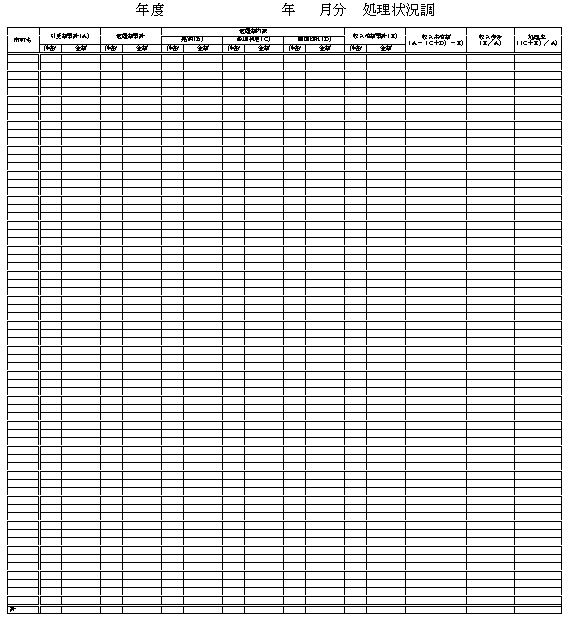平成16年4月16日
三重地方税管理回収機構訓令第10号
|
|
|
| 改正 | 平成17年3月14日三重地方税管理回収機構訓令第12号 | 平成18年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第4号 |
| 平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第6号 | 平成21年9月1日三重地方税管理回収機構訓令第3号 |
| 平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第8号 | |
1 この要領は、三重地方税管理回収機構(以下「機構」という。)の徴収金の収納に係る事務について、必要な事項を定めるものとする。
2 徴収担当職員は、納税者が機構の窓口で納付書(会計規則第4号様式その6)により納付する場合を除き、現金又は有価証券の払込みを受けるときは、滞納整理票(マ整3様式)により納付すべき金額を確認すること。
3 徴収担当職員は、現金を受領した場合は、金額を確認後、当該受領に係る機構領収証書(会計規則第4号様式その7)を作成し、納税者に交付する。
機構領収証書は、徴収担当職員名により交付するものであること。この場合において、徴収担当職員は責任区分を明らかにするため、氏名を自署すること。
有価証券による払込みを受けたときは、15からの「納付又は納入の委託」の取扱いによること。
4 徴収担当職員は、現金を受領した場合は直接徴収金引継書(
収納第1号様式その1)と現金出納票(
収納第1号様式その2)を作成し、直接徴収金引継書、現金出納票、機構領収証書(副)及び現金を会計管理者へ引き継ぐ。
5 電算システムにより未納額を確認し、納税者に対し納付額の確認をすること。
納税者が納付書を持っていない場合は納付書を作成すること。
6 納税者から現金による払込みを受けたときは、当該納付書に記載された金額と現金を照合確認すること。
7 徴収担当職員は、納付書に現金等を添えて会計管理者に回付すること。
会計管理者は、回付を受けた納付書と現金の金額を照合確認し、当該納付書に領収日を記入し、領収日付印を押印すること。
押印後、会計管理者は、納付書の領収証書部分を切り離し再び徴収担当職員に回付し、その他の部分と現金は会計管理者が手元に保管する。
徴収担当職員は、領収日及び領収日付印の押印を確認のうえ、納税者に領収証書を交付すること。
8 会計管理者は現金を受け入れたら、当日中における現金を集計して、窓口収入日計表(
収納第2号様式)を作成するとともに、領収済通知書部分を切り離し、納付書部分を添付する。
会計管理者は、当該窓口収入日計表の記載金額と、当日中における領収日付印押印済みの納付書部分の合計金額を照合し確認すること。
9 会計管理者は徴収担当職員より現金及び直接徴収金引継書等を引継ぎ後、又は窓口収入日計表を作成後、当該直接徴収金引継書、窓口収入日計表の記載金額をもとに、収入金払込書(会計規則第4号様式その10)を作成するとともに受入金額等を管理者に通知すること。この通知は受入決議書に変えることができる。収入金払込書の番号は年度毎の連番とする。
10 会計管理者は、現金の受払いを現金出納簿(市販のもの)の受払欄に登載し整理すること。
11 会計管理者は、現金を指定金融機関に払い込む場合は、収入金払込書により、当日中に払い込むものとし、できる限り現金は手元に保管しないようにすること。
12 会計管理者は指定金融機関より領収証書(払込書)を受け取ったら、領収日付順に綴じ保管すること。
13 納付書部分を徴収第一課又は徴収第二課に回付し、納付のあったことを連絡する。
14 直接徴収に係る機構領収証書(副)及び窓口徴収に係る領収済通知書は、日計日毎に一時保管し、指定金融機関から届く当該払込みに係る領収の通知があったときに、消込業務へ引き継ぐ。
15 未納額の確認をし、提供のあった有価証券の額面を確認する。併せて取立費用を現金で受領し、納税者に納付(納入)受託証書(省令第1号の2様式)(正)を交付するとともに、領収証書等は取立後、送付する旨を伝える。
16 徴収担当職員は、当該有価証券に相当する納付書を作成し、取立費用の金額で、受入手数料入金票を作成する。
納付(納入)受託証書(副)、納付書、受入手数料入金票及び当該有価証券、取立費用は遅滞なく会計管理者に引き継ぐこと。
17 会計管理者は徴収担当職員より納付(納入)受託証書(副)、納付書、受入手数料入金票及び当該有価証券、取立費用の引継ぎを受けたら、速やかに納付(納入)受託証券整理簿(
収納第3号様式)及び納付書に所要の事項を記載する。
18 納付(納入)受託証書(副)は整理番号順に並べ保管する。
19 指定金融機関へ納付書、有価証券、受入手数料入金票、手数料、納付(納入)受託証券整理簿を送付し、取立のための再委託をする。
20 指定金融機関より受託証券整理簿、手数料計算書を受領する。
手数料計算書は、領収証書が届くまでのあいだ、一時保管する。
21 再委託による納付手続き完了後、指定金融機関より領収証書を受領する。
22 会計管理者は納付(納入)受託証券整理簿と領収証書に所要事項を記載する。
23 領収証書に、保管していた手数料計算書を添えて、納税者へ送付する。
24 委託を受けた後において次のいずれかに該当するときは、その委託を解除し、その委託に係る有価証券は委託者に返すこと。
(1) 現金による納付若しくは納入、賦課の取消又は過誤納金の充当等により納付若しくは納入の委託を受けた有価証券に係る徴収金の徴収を目的とする権利が消滅し若しくはその徴収金が減額となったとき。
(2) 納付若しくは納入の委託を受けた有価証券の取立が確実でないと認められるに至ったとき又は不渡りとなったとき。
25 会計管理者は、納付又は納入の委託を受けた有価証券を24の理由により委託者に返すときは、納付(納入)受託証券整理簿に所要事項を記載するとともに、徴収担当職員に連絡する。又、遅滞無く当該有価証券と引換えに交付した納付(納入)受託証書正本を取りもどし朱斜線を引き書損の処理をすること。この場合において受託者が納付(納入)受託証書正本を紛失した等の理由により、当該納付(納入)受託証書正本を取りもどすことが困難な場合は、返すべき有価証券を受理した旨の書類をもって、当該取りもどすべき納付(納入)受託証書正本にかえることができる。
26 納付又は納入の委託を受けた有価証券が不渡りとなった場合において、不渡手数料を必要とするときは委託者に支払わせること。
27 出納員は、納人以外の第三者から、債権差押、公売、交付要求、徴収の嘱託、その他により現金等を受領したときは、納人外領収証書(会計規則第4号様式その8)を当該第三者に交付すること。
28 受領した現金等は、会計規則第98条の規定により、歳入歳出外現金受入決議書(会計規則第39号様式その1)を作成し、管理者に受入れの決裁を受ける。決裁に基づき、受入れのための現金収納票(保管会計)(会計規則第4号様式その9)を作成する。
歳入歳出外現金受入決議書と現金収納票を会計管理者へ引き継ぐ。
ただし、受領した現金が、当日中に徴収金等に充当できるものについては、当該払込みに係る納付書を作成し現金を添えて、会計管理者へ引き継ぐ。引継ぎ後、9からの「直接徴収、窓口徴収における現金の払込み」の手続きにより処理すること。
29 会計管理者は決裁終了後、現金出納簿に登載して、その出納状況を明らかにすること。
30 会計管理者は、歳入歳出外現金受入決議書が作成されている現金等については、現金収納票(保管会計)を添えて指定金融機関に払い込むこと。
31 支払い担当職員は、徴収課より配当計算書等の引継ぎを受けたら、納付書の金額と配当計算書の金額の確認を行う。確認済みの配当計算書等に基づき歳入歳出外現金払出命令書(会計規則第44号様式)を作成し、管理者の決裁を受ける。決裁後、歳入歳出外現金払出命令書と納付書を会計管理者に引き継ぐ。この場合に機構が収納すべき滞納処分費があるときは、当該金額に係る納付書(会計規則第4号様式その2)を添付すること。
32 会計管理者は、引継ぎを受けたら、52からの「指定金融機関への支払依頼」の手続きを準用し徴収金の振替手続きを指定された日で行うこと。また、機構が収納すべき滞納処分費があるときは、一般会計への振替手続きも行うこと。
その場合に、文中の「各市町」を「各債権者」と、「口座振替依頼書」を「納付書」及び「口座振替依頼書」と読み替えるものとする。
(1) 出納員は、公売の参加者より公売保証金を受領したときは、預り証及び受領証書を交付すること。
(2) 最高価申込者及び次順位買受申込者以外の参加者の保証金は、入札終了後、当日中に預り証及び受領証書と引換えに返還をする。
(3) 最高価申込者及び次順位買受申込者の公売保証金は、公売代金の納付があるまでのあいだ、28により、指定金融機関に預託すること。
34 支払い担当職員は、徴収課より公売代金の納付の連絡を受けたら、最高価申込者については、会計規則第105条の規定により、歳入歳出外現金収納更正決議書(会計規則第45号様式)を作成し、公売保証金から公売代金への収納更正の手続きを行い、更正通知を会計管理者に通知する。
次順位買受申込者の保証金については、歳入歳出外現金の払出手続きを行い返還する。
35 電算システムにより未納額を確認し、納税者等に対し納付額の確認をするとともに別途手数料が必要なことを伝える。
郵便局の郵便振替払込請求書兼受領証に、郵便局で払い込むための必要事項を記入し、送付する。
36 会計管理者は、郵便局より払込取扱票が送付されたときは、郵便振替受払通知票の記載金額と、払込取扱票の合計金額を照合確認したのちに、小切手振出票(
収納第4号様式)、収入金払込書を作成し、会計管理者名による小切手を振り出す。なお、受入決議書については窓口徴収分に合わせて作成する。
会計管理者は、当該収入金払込書に小切手で出金した現金を添えて、指定金融機関へ払い込むこと。
37 会計管理者は、納税者に対し徴収金の領収証書を作成し、送付する。
38 会計管理者は、払込取扱票の送付を受けたら、払込取扱票の写しを徴収課へ回付し、納付があった旨を連絡するとともに、払込取扱票を日計日毎に一時保管し、指定金融機関から届く当該払込みに係る領収の通知があったときに、消込業務へ引き継ぐ。
39 会計管理者は、指定金融機関より受領した領収済通知書、収入金集計表(
収納第5号様式)の金額を突合すること。一致しない場合は、指定金融機関にその旨を連絡し、訂正すること。
40 指定金融機関から届いた領収済通知書に、機構が保管している領収済通知書等を合わせ、整理すること。この場合に、収入金払込書の領収済通知書は末尾に束ねることとする。
41 消込担当者は、整理済みの領収済通知書の引継ぎを受けたら、領収済通知書の情報をもとに、収納情報の消込を行う。
42 消込は、情報を更新する対象となる滞納状況を電算システムにより照会し登録を行い、登録後、収納情報に誤りがないかの確認を行い、消込済の確認印を領収済通知書に押印する。
43 消込後、消込情報一覧表(
収納第6号様式)を日計日毎に作成し、徴収担当職員に消込の情報を回付する。
44 市町から引継事案収納通知書(移管規則第10号様式)、収納金明細書(移管第17号様式)が送付されたときは、消込担当者は収納金明細書を領収済通知書とみなして消込を行う。ただし、電算システムに収納情報を入力する場合に、収納金明細書による消込であることを電算システムに登録しておくこと。
45 消込担当職員は、前月分の日計の消込が完了したら当該月分の収納一覧表(
収納第7号様式)を作成する。
ただし、3月分については、月初めから15日までの該当期間の消込が完了したら、収納一覧表を作成するものとし、15日の翌日から月末までの消込については、翌月に収納一覧表を作成する。
収納状況を市町別に集計し、市町別集計表(
収納第8号様式)を作成すること。
46 市町別集計表の合計は、指定金融機関から届く前月の月計表と必ず照合、確認を行うこととし、3月分の当月作成分については、該当期間の日計表の合計と必ず照合、確認を行うこと。
確認後、収納一覧表と市町別集計表を支払い担当職員に引き継ぐ。
47 支払い担当職員は、市町別集計表の合計額を支払額として、歳入歳出外現金払出命令書を作成した後、収納一覧表、市町別集計表、債権者内訳表(会計規則第12号様式その2)を添付し、決裁を受けること。支払日は、15日までとするが、3月分の当月支払い分については月末までとする。
支払先の口座については受入口座届出書(
収納第9号様式)により届出のあった口座を指定すること。払出命令決裁後、歳入歳出外現金払出命令書を会計管理者へ引き継ぐものとする。
48 支払額の決定業務で作成した収納一覧表を基に、収納状況を個人別に分類し、一人別徴収金明細書(
収納第10号様式)を作成する。ただし、同一人で市町が異なる場合は市町別に分類した一人別徴収金明細書を作成する。
49 一人別徴収金明細書を同一市町毎にまとめて、市町別の集計を算出し、払込通知書(移管規則第9号様式)を作成する。
なお、払込通知書には振込予定日を記載する。ただし、事前に通知をした場合は、記載を省略することができる。
51 送付伺いの決裁と指定金融機関の支払依頼を終了後、払込通知書に管理者の印を押印し、一人別徴収金明細書を添えて、速やかに該当市町へ送付する。
52 会計管理者は歳入歳出外現金払出命令書の引継ぎを受けたら、内容を審査する。
53 担当職員は、歳入歳出外現金払出命令書を基に、公金支払依頼書(会計規則第17号様式)と各市町毎の口座振替依頼書(会計規則第18号様式)を作成する。
54 指定金融機関へ支払いを依頼するため、公金支払依頼書(控)(会計規則第17号様式)、口座振替依頼書(控)(会計規則第18号様式)により、公金支払依頼書、口座振替依頼書を添付して、決裁を行う。
決裁終了後、公金支払依頼書に会計管理者印を押印し、口座振替依頼書、公金支払依頼書領収書を添付して指定金融機関に送付し、支払いの依頼をし、公金支払依頼書(控)及び口座振替依頼書(控)は支払関係書類として保管すること。
55 指定金融機関から、公金支払依頼書領収書が送付されたら、年度別及び月別に支払関係書類として保管すること。
57 支払証拠書類となる歳入歳出外現金払出命令書、公金支払依頼書(控)、口座振替依頼書(控)、公金支払依頼書領収書を会計規則(証拠書類の編綴)の手続きに従い、月別に編綴し保管すること。
58 月末現在の状況について、次に掲げる帳票を作成すること。
附 則
(平成18年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第4号) 附 則
(平成19年4月1日三重地方税管理回収機構訓令第6号) 附 則
(平成21年9月1日三重地方税管理回収機構訓令第3号) 附 則
(平成27年3月20日三重地方税管理回収機構訓令第8号) 2 この要領の施行前に旧要領の規定に基づき作成されている帳簿及び用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

収納第1号様式その1
(第1の4関係) 
収納第1号様式その2
(第1の4関係) 
収納第2号様式
(第1の8関係) 
収納第3号様式
(第1の17関係) 
収納第4号様式
(第2の36関係) 
収納第5号様式
(第3の39関係) 
収納第6号様式
(第3の43関係) 
収納第7号様式
(第4の45関係) 
収納第8号様式
(第4の45関係) 
収納第9号様式
(第4の47関係) 
収納第10号様式
(第4の48関係) 
収納第12号様式
(第5の58関係) 
収納第13号様式
(第5の58関係) 
収納第14号様式
(第5の58関係)